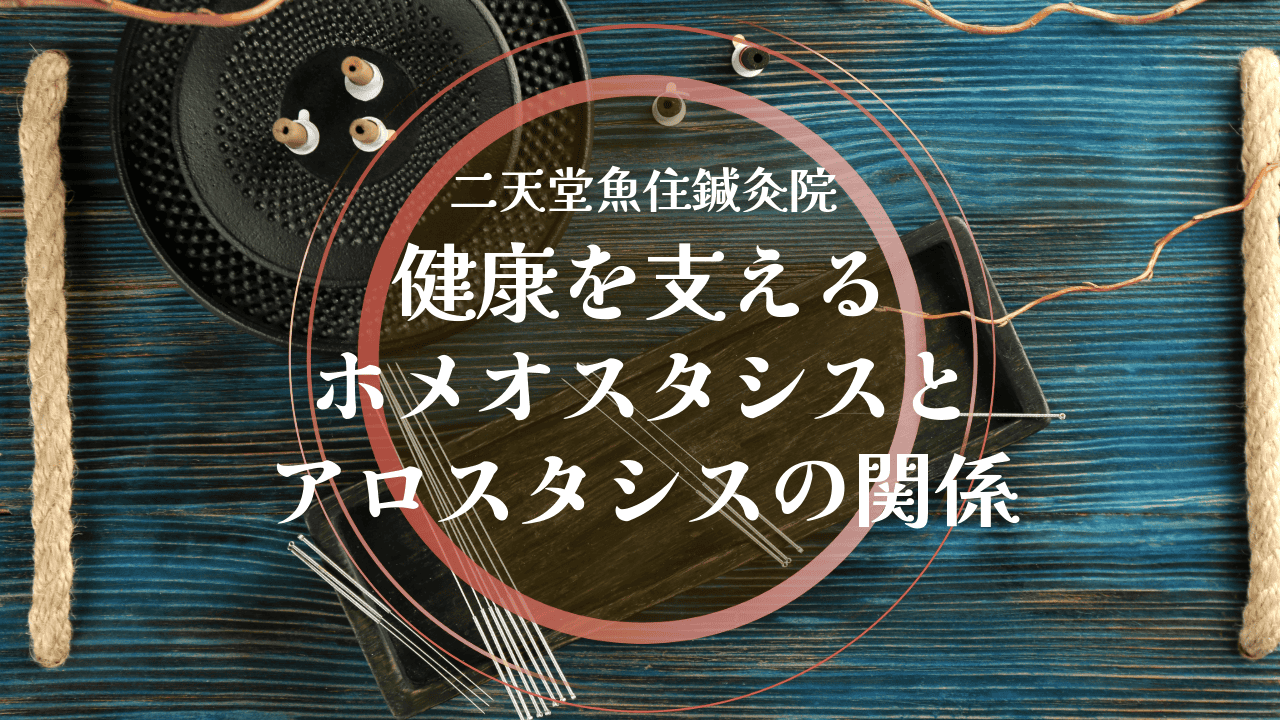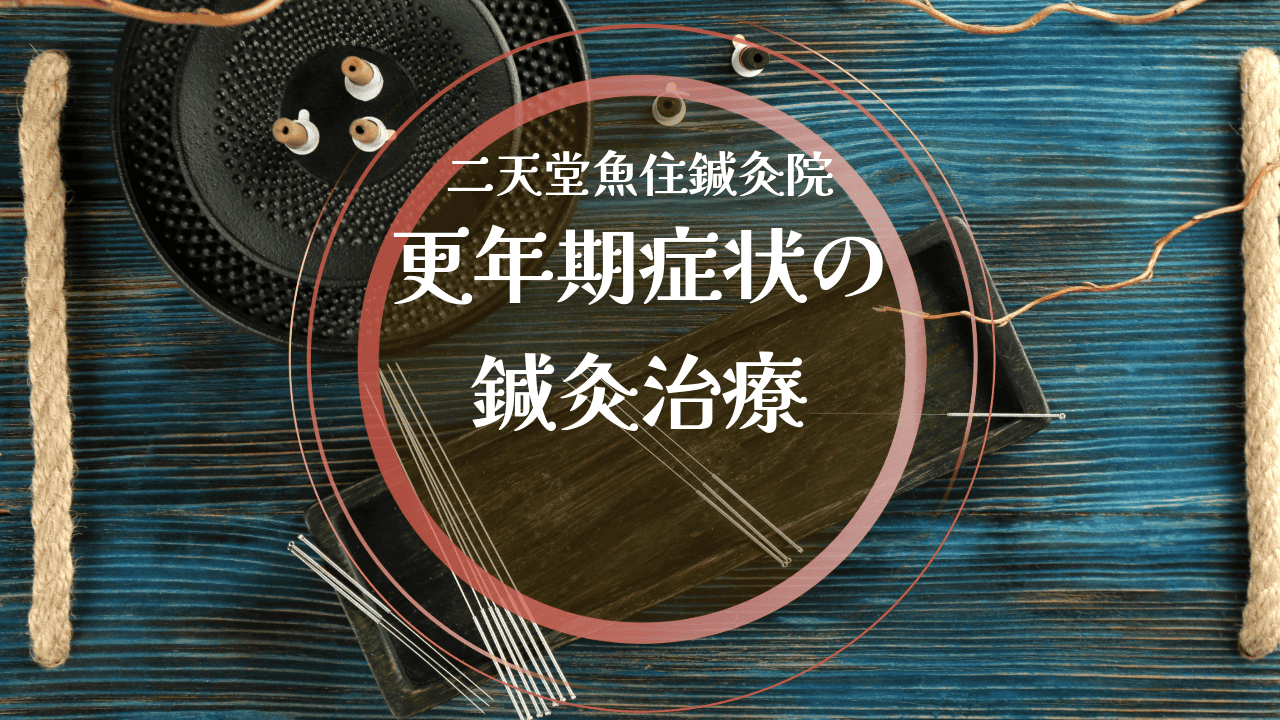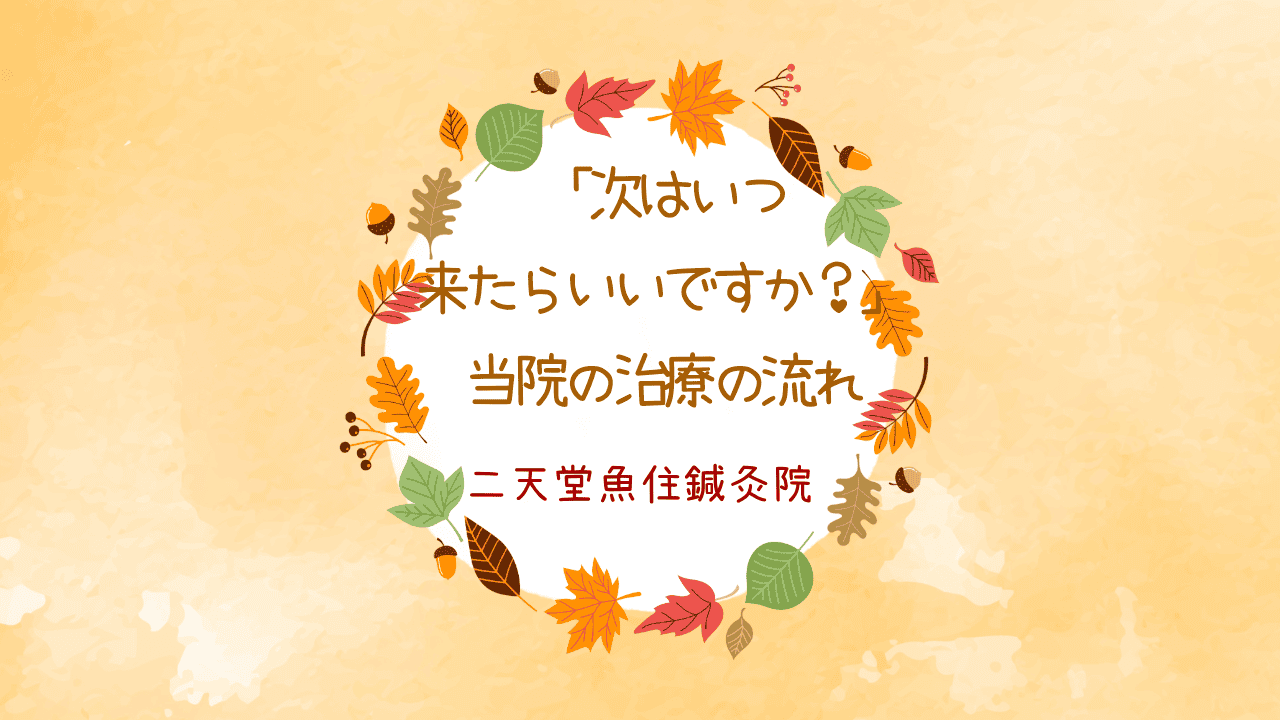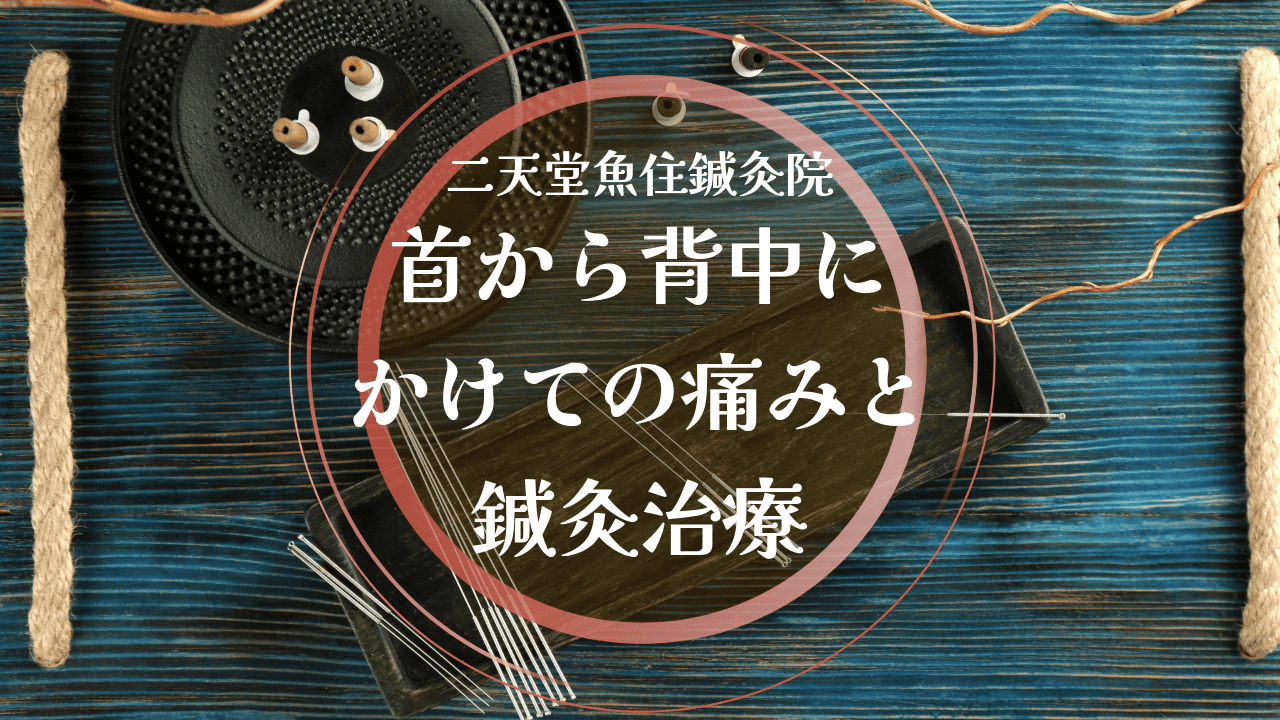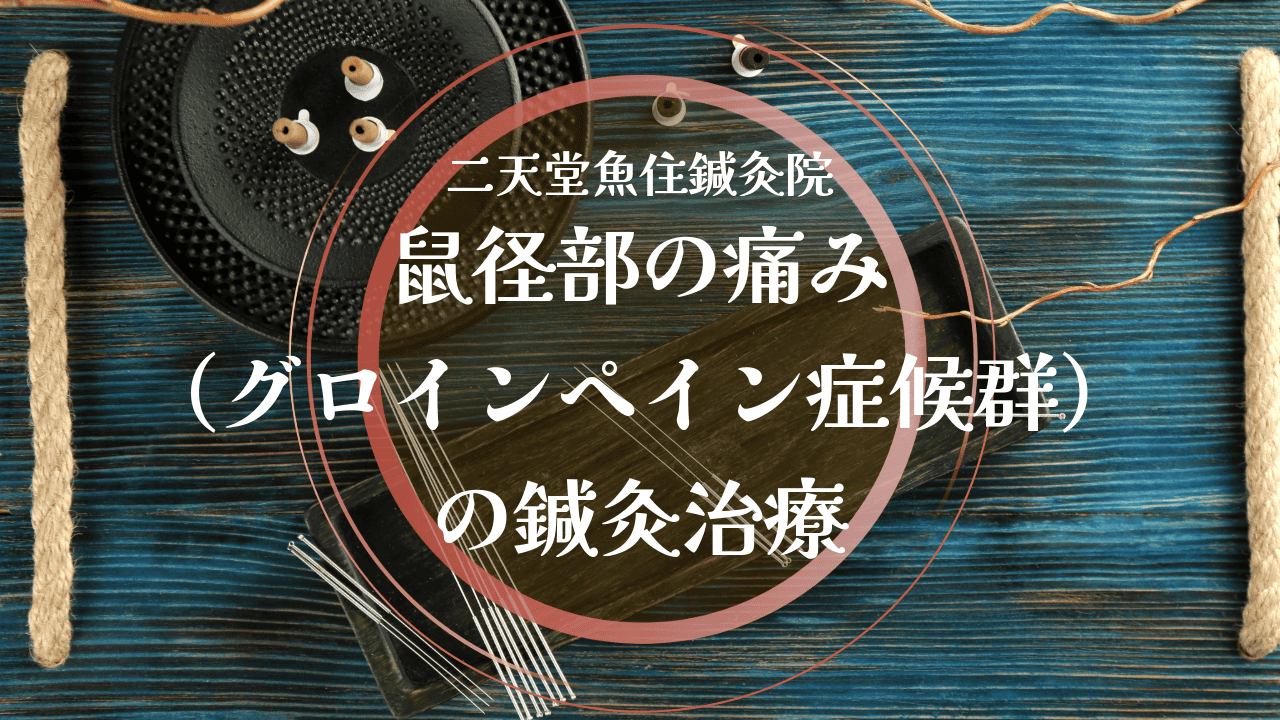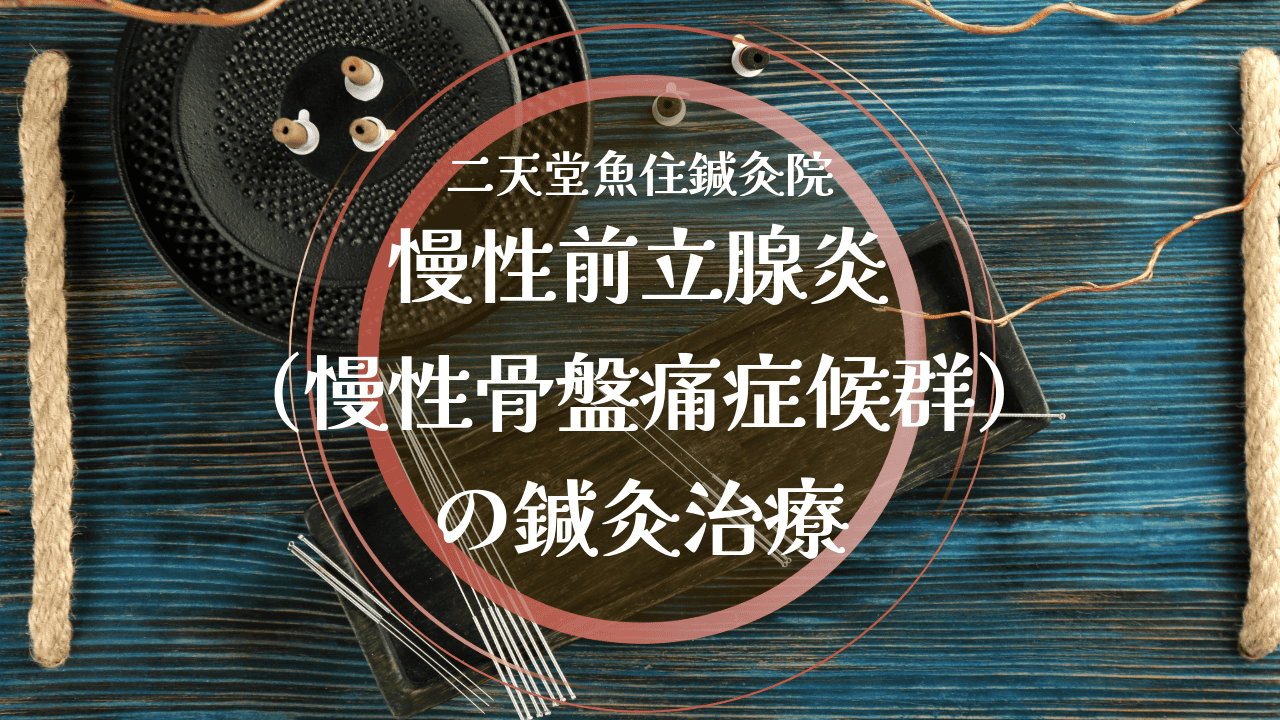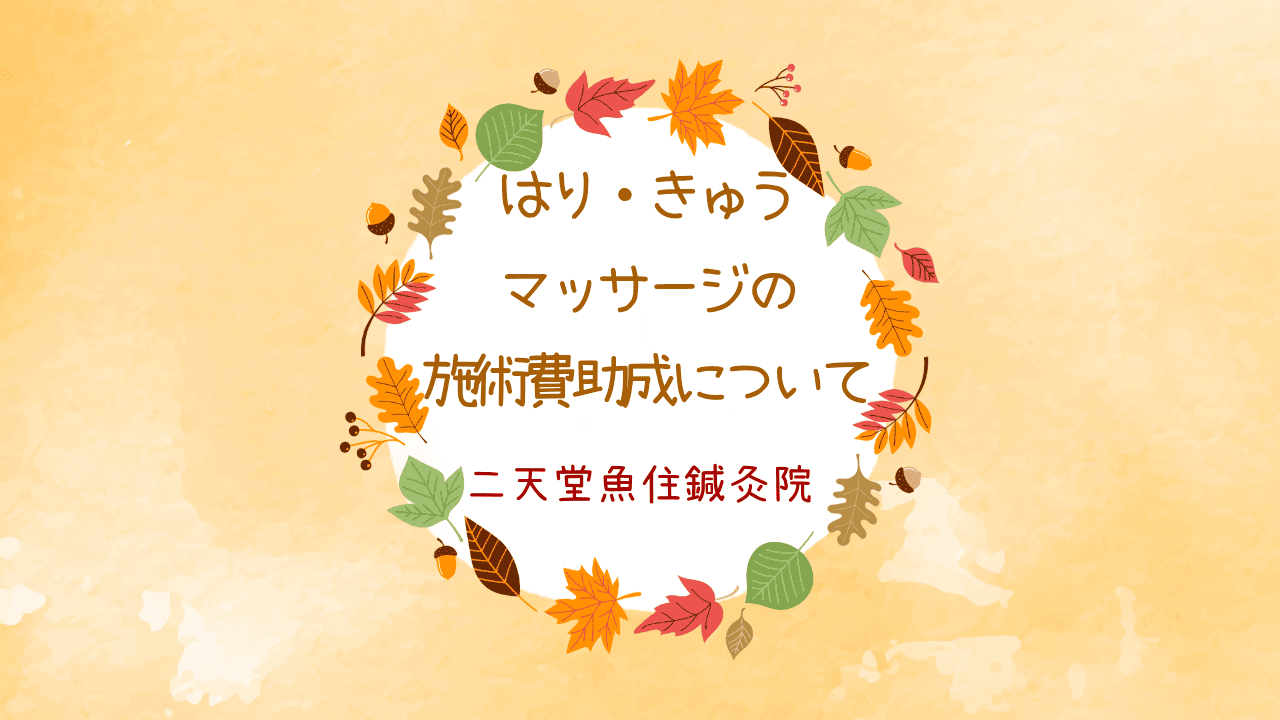こんにちは、二天堂魚住鍼灸院の宮上智志です。私たちは、ホメオスタシス(生体の恒常性)については学校教育でも勉強するのでよく知っています。しかし、アロスタシス(動的適応能)は、あまり知られていないです。今回の記事をきっかけに、アロスタシスがうまく機能する良好な適応状態と、過度な適応が身体に及ぼす負荷「アロスタティックロード」について関心を持っていただけたら幸いです。また、職業柄避けられない“身体の癖”を、遠ざける何かを見つけるヒントになることを期待しています。
ホメオスタシス(生体の恒常性)とアロスタシス(動的適応能)

私たちの身体には、ホメオスタシス(Homeostasis)という素晴らしい機能が備わっています。これは、生体の恒常性を指し、外部環境や内部の変化に関わらず、身体の状態(体温・血糖・免疫)を一定に保つことを言います。そのおかげで我々は、呼吸・循環・排泄・食物摂取の機能が正常に保たれ、健康を維持しています。このホメオスタシスと深く関係しているのが、アロスタシス(Allostasis)です。これは、動的適応能を指し、環境の変化に伴いその都度調節される機能で、自律神経とも密接な関係にあります。例えば、駅に向かった子供に忘れ物を届ける緊急の要件です。駅に向かって大急ぎで駆け出します。アロスタシスにより各種の機能が変化し、体内の環境を変化させます。無事に列車が出る前に子供に出会うことができました。身体は、咄嗟の変化や調整が不要となり、ホメオスタシスによって元に戻ります。運動などの一時的なアロスタシスは、代謝の調節機能を刺激するため健康に良いと考えられています。
アロスタティック・ロード(アロスタティック負荷)

運動ストレスに対してアロスタシスがうまく機能すれ ば良好な適応状態が生まれ、パフォーマンスも増大しますが、運動ストレスが強すぎれば適応能力が及ばず、身体が障害されます。 これをアロスタティックロード(Allostatic load)と言います。身体は、ストレス反応を繰り返すだけでなく、原因が解消後も反応が長引いたり、その他の反応が不十分になって新たなストレス反応を引き起こすなど、体調不良の原因になります。ですから 過度な環境への適応が限界に達すると、健康維持の負担となるケースになります。
これは、心理的ストレスでも起こり得ます。強い緊張やプレッシャーを受ける環境は、どうでしょうか?ピリピリとした空気を感じながら働き、些細なことにも責任を問われる現場なら憂鬱になるのも当然のことです。そのうちに、いつまた上司に怒られるかと待ち受けるようになります。この状態も、アロスタシスによる機能調整を継続させる「アロスタティック・ロード」です。交感神経優位が続き、ホルモンの値も変化するため、小さなことでも敏感に反応するようになります。この機能自体は正常ですが、不適切な状況で継続すると、自律神経がバランスを崩し始めます。消化不良や睡眠障害に加え、ちょっとした物音にも敏感になるなどの徴候も見られ、思考もネガティブに傾きます。この状態が長引けば、職場とストレスが直結した「思考のバイパス」とも言える脳神経の回路ができあがります。現場では、無意識のうちに(状況の判断に関係なく)体内でストレス反応を起こし、身体は多少なりとも緊張した状態になります。これを限界まで耐え続けるか、環境を変えるか、肩にのしかかる緊張が、さらなるストレスになります。ですから、選択の余地がなく頑張り続けることで、負の連鎖に発展する事例もあるのです。
東洋医学の思想と解剖学的ポイント

東洋医学では、生命活動の総称として表現されるものに「神」(しん)があります。これを観察することを「望神」(ぼうしん)と言います。広義の「神」とは、生命活動が外部に現れたものをいい、精神・意識・顔色・眼光・言語の応答・身体の動きの状態などが含まれます。これらの観察で、正気の盛衰、病状の軽重、予後の良不良を初期的に判断します。特に目には、「神」の状態がよく現れるので、目の輝きがあるか、生き生きしているか、動きの状態はいいかなどを診ることは重要です。
人の脳には、額(ひたい)のすぐ後ろ、前の方に、前頭前野と呼ばれる場所があります。 前頭前野は、記憶や感情の制御、行動の抑制など、さまざまな高度な精神活動を司っている、脳の中の脳とも呼ばれている重要な場所です。ここには、精神活動に関連があることを表す「神」の字がつく経穴(けいけつ)ツボがあります。”神庭(しんてい)”と”本神(ほんじん)”や”四神聡(ししんそう)”です。鍼灸治療では、この「神」に効く経穴の周辺に施術することも多いですから、患者さんは仰向けで横になりしばらく安静にしてもらいます。
参考書籍 編者名.公益社団法人東洋療法学校協会 著者名.教科書検討小委員会 「新版 東洋医学概論」 発行所,医道の日本社,出版2019年
まとめ

私は今回、職業柄避けられない“身体の癖”と自律神経の関わりをテーマに記事を書きはじめました。しかし、自律神経の果たす役割は壮大にして緻密です。解剖学・生理学の説明もたくさんする必要があります。どうしても私の能力では、まとめられません。そんなとき、出会ったのがアロスタティック・ロードです。知れば知るほど、患者さんの背景について共感の姿勢が深まるのです。理屈抜きに、胸に刺さる感じです。自分自身の社会人経験も相まって、特に”日本人の気質に沿った”反応と感じるのは私だけでしょうか?我慢強く働くことが度を過ぎると病気になるストーリーが見えてくるではありませんか。これは正に、”身体の癖”として、本来のバランスを崩すしている患者さんの多くに当てはまっているように思えるのです。日本には、「肩を落とす」「下を向く」「背中が物語る」「目が回る」などの表現がありますが、ずっと肩を落とし下を向いていたらどうなるでしょう。精神的ストレスの回路が脳にも影響しているとすれば、本来の姿勢のことをイメージできなくなっているのも理解できます。このように、無意識のうちに身体が緊張して動きが失われた部位では、筋膜などの癒着が起こるのです。あらゆる器官を覆うファシア(Fascia)のつながりは、他のところにも波及しますから心身の不調はどこに現れても不思議ではありません。その方が本来持っている持病や体質にも悪影響を与えることもあるでしょう。頭痛や喘息・アトピーなどの症状が心身のコンディションに左右されることは容易に想像できます。これは心身が発達途中の子供社会でも、同じではないでしょうか。それほどまでに、”良好な適応状態”が複雑化しているのが現代社会なのかも知れません。人体を構成するファシアについても詳しくまとめたページもございます。ファシア(Fascia)とはの記事もぜひご覧ください。
鍼灸治療で用いる経穴(けいけつ)ツボは、治療ポイントとしてだけではなく、不調の反応が表れる”反応ポイント”としての側面があります。ですから古代人は、病症ごとに反応が出ている箇所を探り当て、経穴(ツボ)として整理していくことで治療の精度や再現性を高めていくことができたのです。当院では、これらを参考にして、頭皮や手足にある経穴を用いた脳神経へのアプローチもケースに応じて行います。これにより、全身性に作用する下降性痛覚抑制系に働きかけてセロトニンやノルアドレナリンの分泌を促し、脳の興奮を抑え、心身をリラックスさせる効果が期待できます。鍼灸施術は自律神経系や免疫系にも働きかけることができる積極的な治療です。心身を緊張から解放し、本来のホメオスタシスの働きを手助けする効果が科学的にも証明されています。もし、お困りの症状で気になることがありましたら、あなたの街の鍼灸院に相談してみましょう。