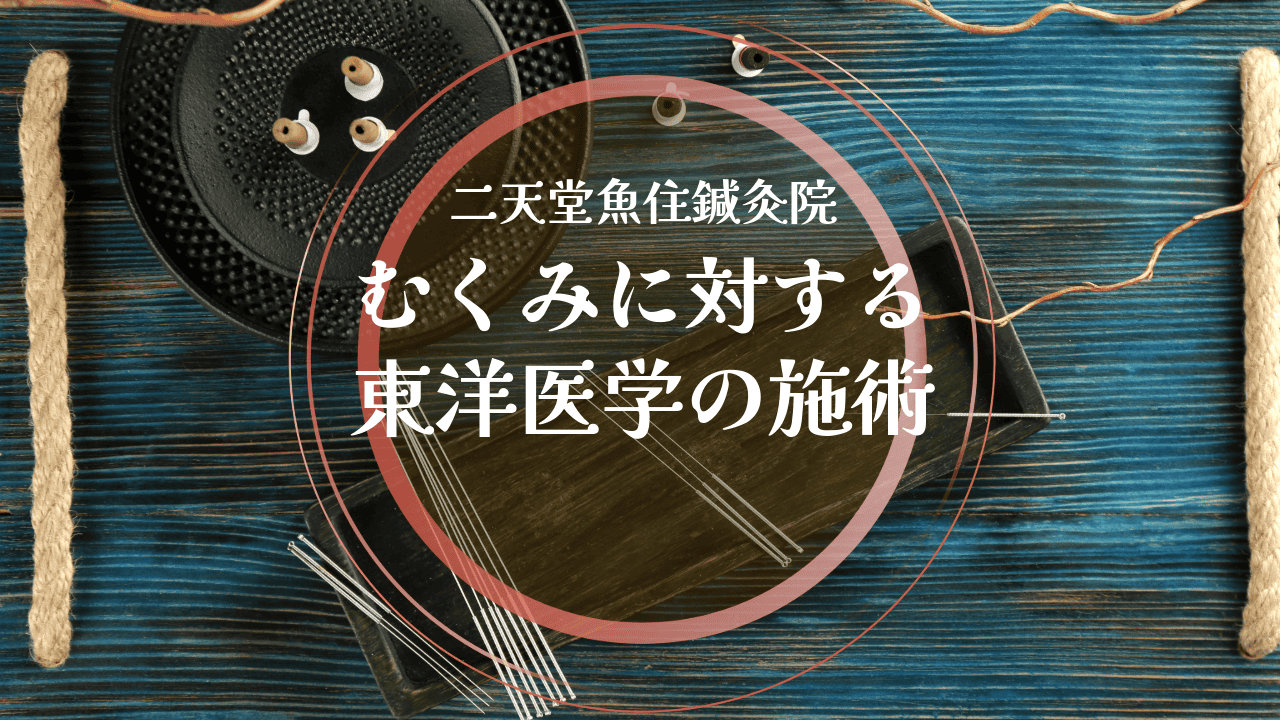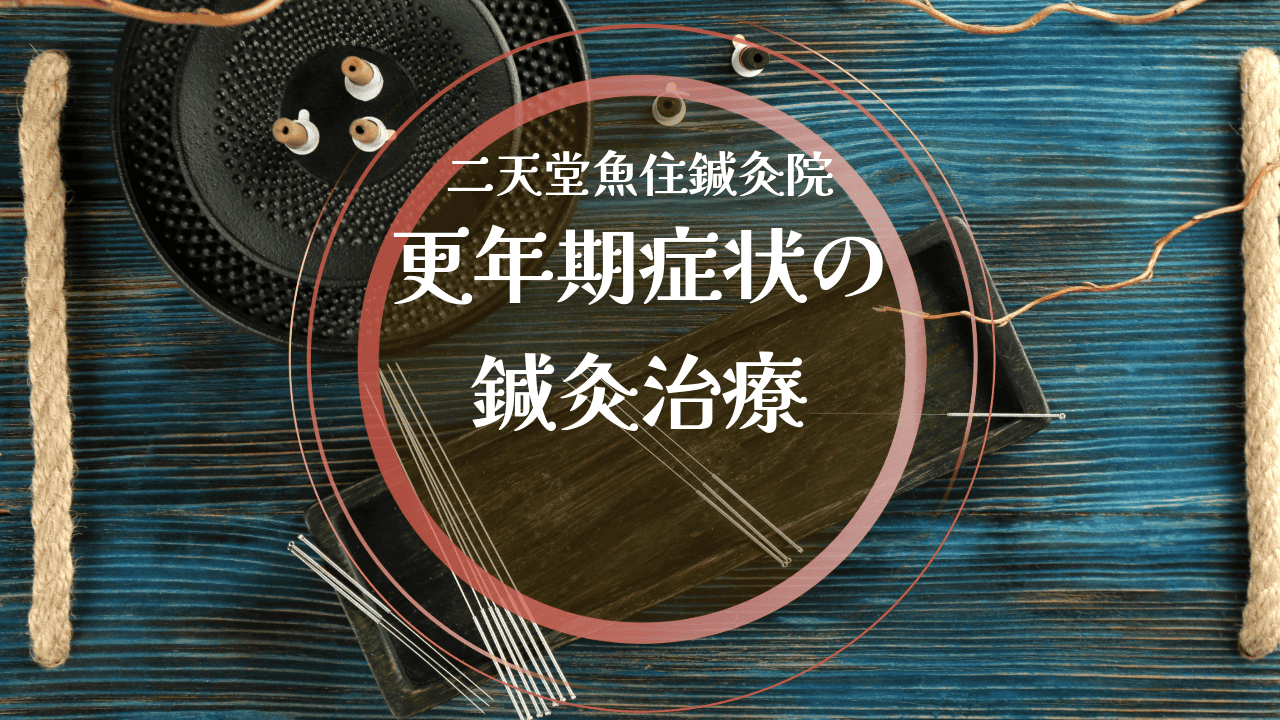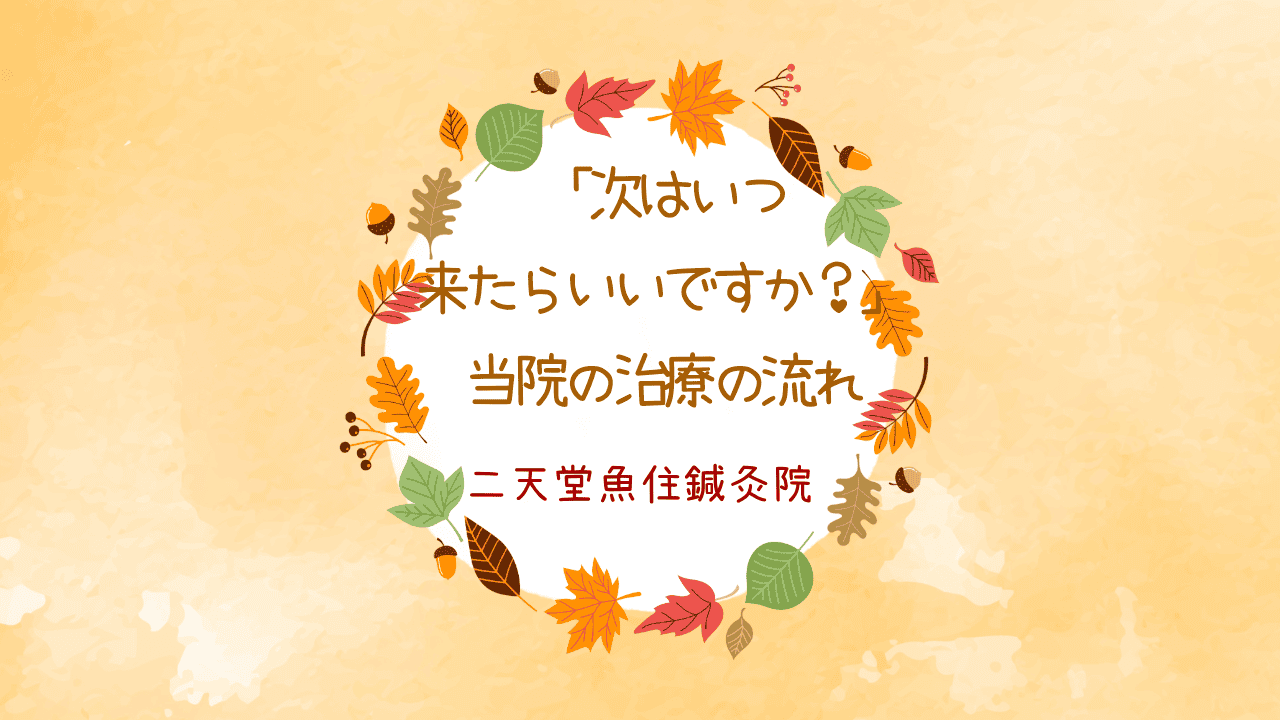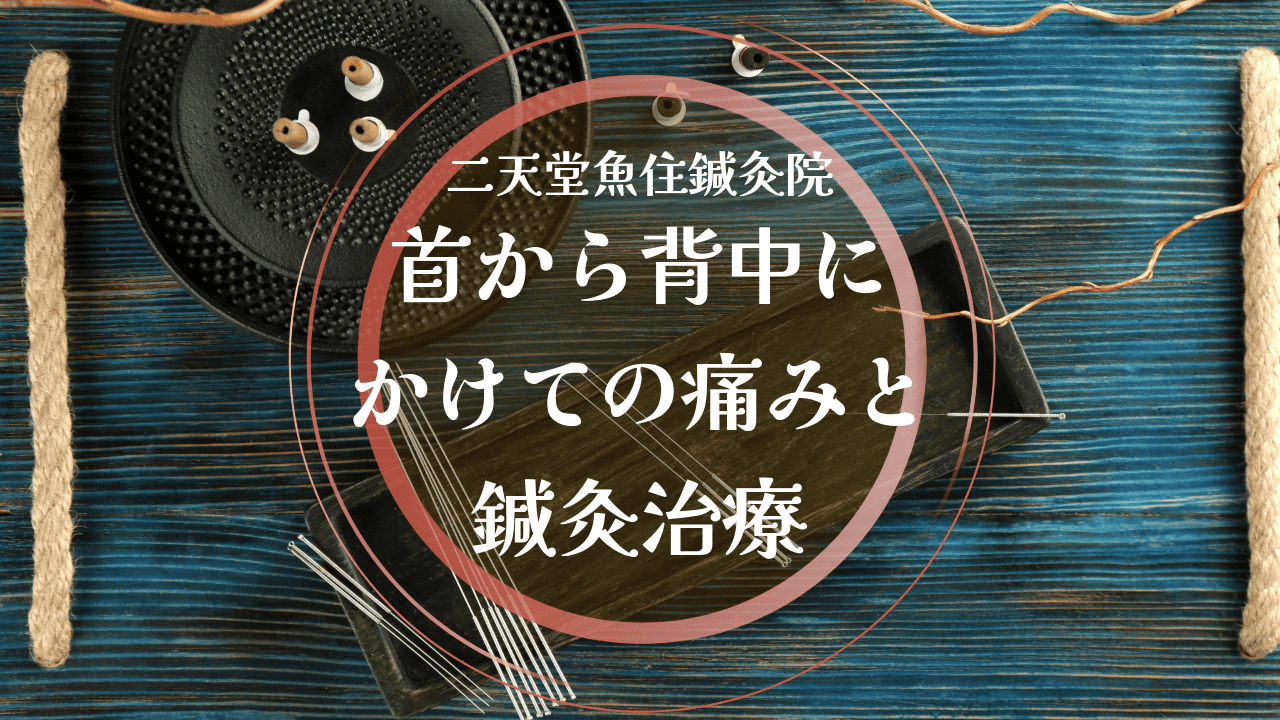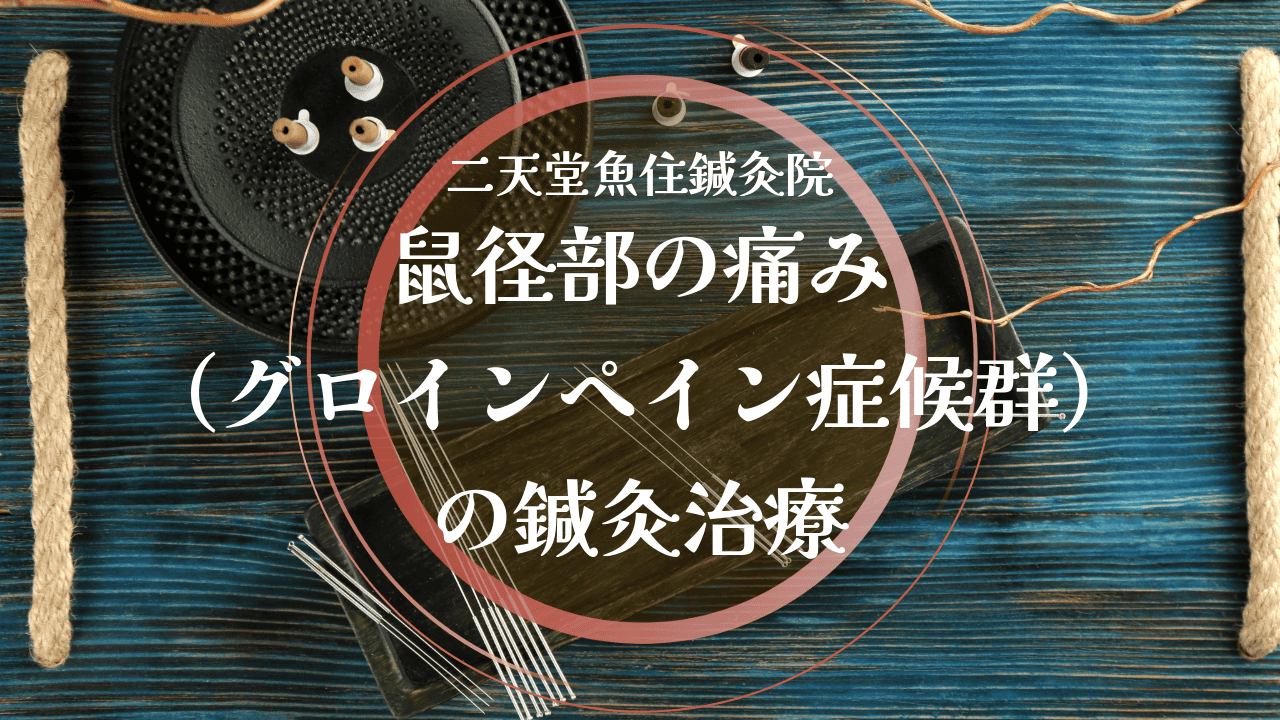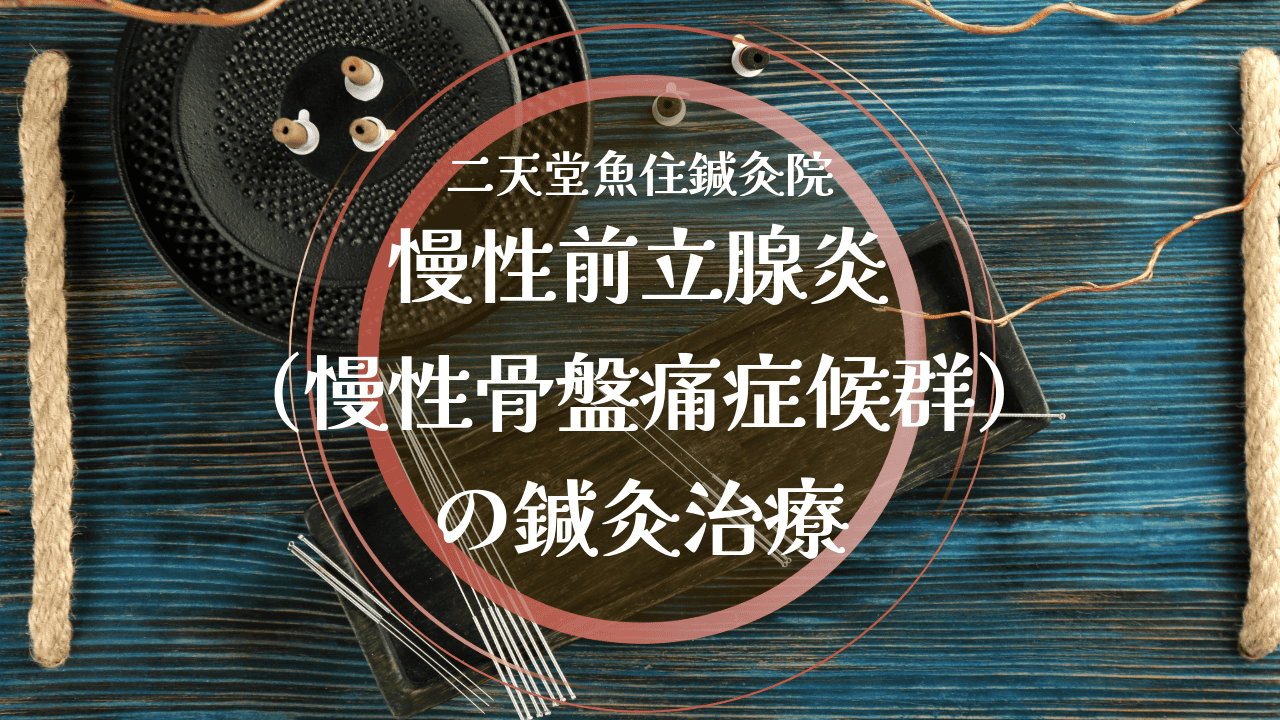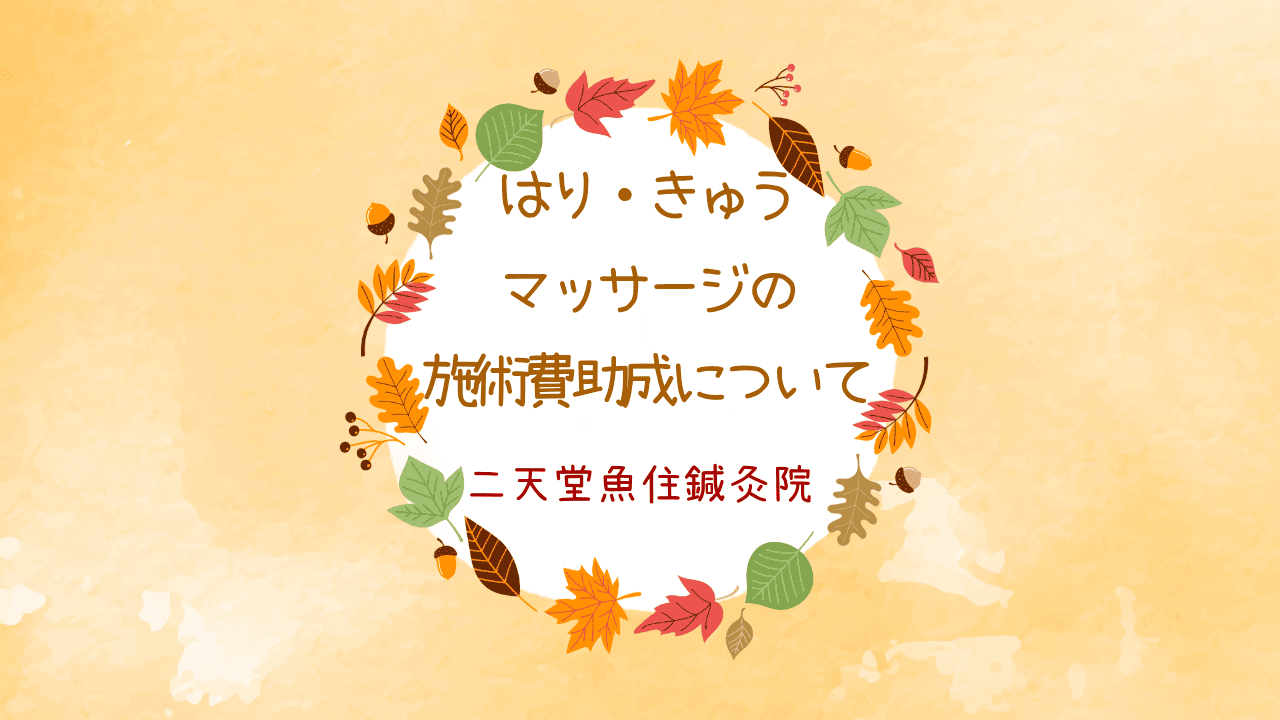こんにちは。兵庫県明石市にある二天堂魚住鍼灸院の宮上智志です。臨床の現場で施術にあたっていると、「むくみ」について悩んでいる方が多いことに気づきます。医学的には「浮腫」と言いますが、何らかの原因によって、皮膚の下に余分な水分が溜まった状態のことを言います。東洋医学は、むくみに対して効果的な治療ができますので、「むくみ」を診るポイントと施術を記事にします。
経絡リンパマッサージ

経絡やリンパの流れが滞ると、むくみや痛み、コリ、疲労、体調不良、免疫力の低下等の症状が現れます。経絡リンパマッサージは、「経絡」と「リンパ」の双方に共通する「流れ」に着目し、その流れを改善していきます。これにより、全身のバランスが整えられた結果、血行の促進と免疫機能の改善がなされると共に、体に溜まった余分な水分や老廃物等を排泄し、体の内側から健康でキレイな体を取り戻すことができます。
リンパを流すには、手を肌に密着させて軽く圧をかけて擦るのが効果的です。単に押すだけよりリンパ循環スピードが約3倍になるという報告があります。さらにリンパマッサージを行う際に、手だけを動かすのではなく、身体のアクティブな動きに合わせて擦るのがよいです。名付けてアクティブリンパマッサージです。身体を動かしながら擦ると、筋肉の伸縮により、リンパがさらに流れやすくなります。
参考資料:社団法人 経絡リンパマッサージ協会ホームページ
参考資料:著者名.経絡リンパマッサージ師.渡辺 佳子.経絡リンパマッサージ協会代表理事.アクティブ・リンパマッサージ. 解消へと導く、6大セルフケア.「Tarzan No.885 たるみ&むくみ セルフケア」.出版社マガジンハウス,出版2024年8月22日,P16
ツボ押し(経穴)

ツボ(経穴)の多くは、経絡と呼ばれる「気」・「血」・「水」の流れの上にあります。「気」とは、目に見えない生体エネルギー、「血」は血液、「水」はリンパ液などの体液です。たとえば足にあるツボ(経絡)を刺激しても経絡を通じて他の部位や、内臓を刺激することができます。むくみの解消には、腎臓や泌尿器にもアプローチできるツボ(経穴)を選べば、体内の余計な水分が排出され、より効果的です。ツボ(経穴)は、神経が多く集まる場所であることも多いです。筋肉の動きがスムーズになり、たるみ改善効果が期待できます。また、「気」の流れがよくなることで、引き締めの効果もあります。
- 翳風(えいふう)・・・淀みやすい 老廃物がたまりやすいポイント。刺激することで顔の血流、リンパの流れの改善が期待できる。
- 欠盆(けつぼん)・・・首から上の血流、リンパの流れを改善。顔全体をスッキリさせるのに効果的 。顔色も良くなる。
- 人迎(じんげい)・・・首の滞りを改善することで、顔への血流を促進。たるみ、むくみに加え、くすみの解消も期待できる。
- 四白(しはく)・・・頬の血行を促しながら周辺の筋肉を刺激し、たるみ・ むくみを改善。
- 頬車(きょうしゃ)・・・小顔効果が高いとされている ツボ。口元のたるみやむくみ 、ほうれい線にも効く。
- 承泣・球後(しょうきゅう・きゅうご)・・・どちらも眼精疲労や目のかすみ、充血に効くツボ。目元のたるみ、むくみ、クマ、小ジワの改善が期待できる。
- 足三里(あしさんり)・・・胃腸などの消化器系を整え、全身の水の巡りをよくする。全身の血流促進効果もある。
- 陰陵泉(いんりょうせん)・・・水分の代謝をアップし、むくみ解消が期待できるツボ。胃腸などの消化器や泌尿器の不調改善にも効く。
- 豊隆(ほうりゅう)・・・体内の余計な水分 ・老廃物をスムーズに排出させる効果がある。陰陵泉と合わせるとより水の流れがスムーズになる。
参考資料:著者名.鍼灸あん摩マッサージ指圧師.柳本真弓.MLAJ医療徒手リンパドレナージセラピスト(上級).ツボ押し. 解消へと導く、6大セルフケア.「Tarzan No.885 たるみ&むくみ セルフケア」.出版社マガジンハウス,出版2024年8月22日,P17.28.29
東洋医学で用いる漢方薬

- 当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん)・・・血行をよくする当帰(とうき)、利尿作用のある茯苓(ぶくりょう)などの生薬を配合。体力の低下、めまいやむくみにも用いる。
- 防已黄耆湯(ぼういおうぎとう)・・・水の巡りを改善する。水太り気味で虚弱体質な方やむくみ、多汗、肥満症に効果がある。
- 五苓散(ごれいさん)・・・水の巡りを改善し、むくみや吐き気に効果がある。口が渇き、尿が少ない方に広く使用される。
- 防風通聖散(ぼうふうつうしょうさん)・・・全身の水の巡りを改善する。太鼓腹の肥満症、便秘、むくみ、のぼせに効果がある。
- 茵蔯五苓散(いんちんごれいさん)・・・余分な水分を排出。吐き気やむくみ、二日酔いにも効果がある。
- 柴苓湯(さいれいとう)・・・炎症を鎮める柴胡(さいこ)や利尿作用の高い茯苓(ぶくりょう)を配合。口が渇き、尿が少ない方使用される。
- 小青竜湯(しょうせいりゅうとう)・・・全身の水の巡りを調節するので、水のような鼻水や痰、むくみにも効果がある。
参考資料:著者名.佐藤弘.東京女子医科大学東洋医学研究所所長,吉川信.東京女子医科大学東洋医学研究所鍼灸臨床施設長.「東洋医学の基本講座」.出版社成美堂出版.出版2013年1月20日,P201
鍼灸の施術
鍼灸の施術は、むくみ(浮腫)に対して高い効果を発揮します。 鍼灸による刺激は血液やリンパの流れを改善し、身体全体の水分バランスを整える作用があります。 特に足のむくみでは、体内の水分が下半身に滞りがちです。 鍼灸はこうした滞りを解消し、余分な水分を排出しやすくする効果があります。当院が鍼灸施術に交える身体をほぐす手技についてまとめたページもございます。ソフトな手技の記事もぜひご覧ください。
まとめ

むくみ(浮腫)の症状は、視診と触診で確認することができます。腕や足の太さに左右差がないか、皮膚の色や硬さに変化がないか。リンパ液が溜まって皮膚が厚くなると、皮膚を引き寄せたときにしわができにくくなったり、皮膚をつまみにくいなどの変化もみられます。
下腿前面などに指腹を用い5mmほどの深さで、10秒間押した時の皮膚圧痕の回復具合を評価します。
- 跳ね返るタイプ・・・熱感も確認します。熱感があれば「炎症性の浮腫」、なければ「リンパ性の浮腫」と推測します。
- 陥没が続くタイプ・・・40秒程度で回復するものには、低栄養などの低アルブミン血症が疑われます。40秒以上残る圧痕性浮腫には、心不全や腎不全、薬剤性などがあります。
むくみ(浮腫)は、毛細血管から細胞の間に流れ出る水分が多くなったり、毛細血管やリンパ管へ吸収される水分が減ることによって起こります。これらの多くは血液の循環が悪くなったときです。ですから日常生活を活動的に過ごすことや、体操などで滑らかに動く筋肉を維持することは、むくみ(浮腫)の予防に高い効果があります。その他にも「冷え対策」は、末梢の血液循環を守るうえで大切です。これは、冬期に限らず冷房にあたり過ぎる冷えも含みます。